児童手当について
児童手当について
児童手当は、高校生年代までの子(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育する者に支給されるものです。本制度は、「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的としています。
支給対象となる児童
国内に住所を有する高校生年代までの児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)
ただし、児童が海外へ留学している場合は対象となる場合もあります。
受給資格者
- にかほ市内に住所を有し、支給対象となる児童を養育している方。父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に児童手当が支給される場合があります。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
- 児童を日本に残し、父母が海外に住んでいる場合は、その父母が受給者として指定した方(日本国内に住む子どもを養育している人)に児童手当を支給します。
申請手続きについて
申請窓口
- 申請窓口は、児童の生計を主に支える方(保護者のうち所得の高い方)が住民票を置いている市役所です。
主に生計を支えている方が単身赴任等でにかほ市以外に住民票を置いている場合は、住所がある市役所で申請をしてください。 - 公務員の方は勤務先から支給されますので、市役所ではなく、勤務先で申請手続きをしてください。
申請期限
出生及び転入の場合は、出生日及び転入予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。
書類審査のうえ、申請手続きをされた翌月分からの支給になります。
申請に必要なもの
- 児童手当 認定請求書
- 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可。)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等、写真つきのもの)
- 請求者の健康保険情報のわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせなど)
- 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
次に該当する方は、1~5に加え、下記の書類も必要になります。
単身赴任等により児童と別居している場合
- 児童の属する世帯全員の住民票の写し(児童の住所がにかほ市にある場合は不要)
- 別居監護申立書
児童が請求者のこどもでない場合
- 養育についての申立書
離婚協議中で父母が別居(住民票も別)している場合に、児童と同居している方が申請する場合
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 離婚協議中であることを証明できるもの。(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など。)
未成年後見人が受給される場合
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 児童の戸籍謄本
父母指定者が受給される場合
父母が海外に居住し、児童が国内に住所を有する場合、日本国内で児童を養育するものを指定した場合、その指定されたものが手当を受け取ることができます。
- 父母指定者指定届受領書
- 父母の海外居住状況の分かる書類
海外に居住する児童について
海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
必要書類
- 海外留学に関する申立書
- 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第三者による翻訳の添付が必要になります。)
- 従前の日本国内での居住状況が分かる書類
次の場合は、手続きが必要です。
すでに児童手当を受給していて、増額となる事由が発生した場合(第2子以降出生など)
- 児童手当の額が増額となりますので額改定手続きが必要です。
児童手当 額改定認定請求書を提出してください。
すでに児童手当を受給していて、減額となる事由が発生した場合(児童の死亡・離婚による児童の減員など)
- 児童手当の額が減額となりますので額改定手続きが必要です。
児童手当 額改定認定請求書を提出してください。
受給者と児童が、他市町村へ転出する場合
- にかほ市での児童手当の受給資格がなくなりますので、消滅手続きが必要です。
消滅届を提出してください。
仕事の都合などで、受給者と児童の住所が別になる場合
- 受給者が転出し、児童がにかほ市に残る場合は、転出する受給者の消滅手続きが必要です。
消滅届を提出し、転出先で新たに申請手続きをしてください。 - 受給者が海外へ転出する場合は、配偶者の方が新たに受給者となりますので、受給者変更の手続きが必要です。
海外へ転出される受給者の方は消滅届を提出し、配偶者の方が新たな受給者として認定請求書を提出してください。
離婚や、主に生計を支える方が変わったなど、児童手当の受給者が変わる場合
- 今までの受給者の消滅手続きと、新たに児童手当の受給者となる方の認定請求手続きが必要です。
今まで受給者だった方は消滅届を提出し、新たな受給者の方が認定請求書を提出してください。
児童手当は消滅日の属する月分までの分が前受給者に支給され、新しく受給者となった方には申請の翌月分からの支給となります。
受給者が公務員になった場合
- 公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。にかほ市での消滅手続きが必要です。
消滅届を提出し、勤務先で新たに申請手続きをしてください。
支給月額
|
3歳未満 (0~2歳) |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 |
- 3歳に達した月の翌月分から3歳以上の金額になります。
- 児童の数え方について、児童手当では経済的な負担等がある大学生年代(22歳到達後の最初の年度末までの子)未満を児童として数えます。大学生年代以上のお子さんについては児童の人数として数えませんのでご注意ください。
支払時期
年6回、2か月分の手当がまとめて支払われます。
| 支払月 | 支払対象月 |
|---|---|
| 4月7日 | 2~3月分 |
| 6月7日 | 4~5月分 |
| 8月7日 | 6~7月 |
| 10月7日 | 8~9月 |
| 12月7日 | 10~11月 |
| 2月7日 | 12~1月 |
支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日の支払となります。
現況届について
現在児童手当を受給している方を対象に、所得の状況やお子様の養育状況を確認するため、毎年6月に現況届を提出してもらいます。
現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受け取れませんので、必ず提出してください。
対象となる方に用紙を5月下旬以降に発送します。
申請書のダウンロード
| 種類 | ダウンロード |
|---|---|
|
【認定請求書】 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合。 |
認定請求書(PDFファイル:344.3KB) |
|
【額改定認定請求書額改定届】 既に手当を受給中の方で、扶養する児童が増減した場合。 |
額改定認定請求書(PDFファイル:123.2KB) |
|
【受給事由消滅届】 転出等により支給を受ける事由が消滅した場合。 |
消滅届(PDFファイル:81.8KB) |
|
【別居監護申立書】 請求者と対象児童が別居している場合。 |
別居監護申立書(PDFファイル:48.3KB) |
|
【児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)】 父母が離婚協議中で別居している場合で児童と同居している者が請求者となる場合。 |
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(Wordファイル:31.1KB) |
|
【口座振替払届出書】 口座の変更をする場合。ただし口座は受給者名義のものに限る。 |
口座振替払届出書(Excelファイル:31.5KB) |
|
【養育についての申立書】 児童が請求者の子でない場合。(両親が亡くなり祖父母が養育している・養子縁組を前提とした再婚 など) |
養育についての申立書(Wordファイル:36KB) |
|
【父母指定者指定届】 父母等は海外に住んでいるが、対象児童は日本に住んでいる場合で、父母等から対象児童を養育しているものとして指定を受ける場合。 |
父母指定者指定届(Excelファイル:556.5KB) |
|
【児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)】 未成年後見人が児童を養育している場合。 |
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(Wordファイル:58KB) |
|
【個人番号変更等申出書】 個人番号に変更、消滅があった場合。(個人番号の変更・離婚等により配偶者等の個人番号を消滅・婚姻等により配偶者の個人番号を新たに登録する など) |
個人番号変更等申出書(Excelファイル:23.6KB) |
各種申請書は窓口にもございます。
提出先
こども家庭センター 子育て支援班(総合福祉交流センター スマイル)
税務課市民サービス班(象潟庁舎)
市民サービスセンター(金浦庁舎)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉事務所 こども家庭センター 子育て支援班
〒018-0402
秋田県にかほ市平沢字八森31番地1
福祉総合交流センター(スマイル)内
電話番号:0184-32-3040
お問い合わせはこちら






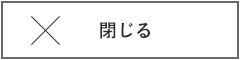

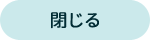
更新日:2025年12月23日