土地
土地について
項目をクリックするとジャンプします。
土地の評価方法
土地については、原則として3年に一度評価替えが行われ、地目別に定められた評価方法により評価します。価格は、売買実例価格をもとに算定した、正常売買価格を基礎として求めます。
イ.宅地の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
- 道路、家屋の疎密度、公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分。
- 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定。
- 主要な街路の路線価の付設。
- その他の街路の路線価の比準、付設。
- 地区・地域内の各筆の評価。
路線価とは?
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
標準宅地とは?
標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価額等を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして、道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
ロ.農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ハ.原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
土地についての特例
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地に対しては、税負担を軽減するため、課税標準の特例措置が講じられています。
住宅用地とは?
住宅用地とは、住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。
住宅用地は次のとおり区分されます。
- 小規模住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分をいいます。 - 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分)をいいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
なお、住宅とは、もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅、アパート、マンションなど)又は、その一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅=事務所、店舗などと居宅を兼ねた住宅)をいいます。
専用住宅などの場合は、その敷地のすべてが住宅用地(家屋の床面積の10倍まで)となりますが、併用住宅の場合は、その家屋全体のうち、居住部分がどの程度あるのかをそれぞれの床面積で判断して、住宅用地(家屋の床面積の10倍まで)を認定します。
居住部分の家屋全体に占める割合(これを「居住割合」といいます。)によって、住宅用地の率が次のとおり定められています。
| 家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|---|
| 地上5階建以上の耐火建築である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
| 地上5階建以上の耐火建築である併用住宅 | 1/2以上3/4未満 | 0.75 |
| 地上5階建以上の耐火建築である併用住宅 | 3/4以上 | 1.0 |
| 上記以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
| 上記以外の併用住宅 | 1/2以上 | 1.0 |
住宅用地に対する課税標準の特例は、賦課期日において、新たに住宅の建設が予定されている土地又は住宅が建設されつつある土地については適用されません。ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱います。
※住宅用地の特例を受けている土地の住宅が火災等により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、火災等の発生後2年度分に限り引き続き住宅用地として取り扱われます。
※管理不全の空家の除却・適正管理を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による必要な措置の勧告の対象となった特定空家等、管理不全空家等の敷地の用に供する土地については、住宅用地特例の対象から除外することとされています。
住宅用地の特例率
住宅用地については、次により計算した額が課税標準額となります。
- 小規模住宅用地…価格×1/6
- 一般住宅用地…価格×1/3
なお、住宅用地に対する課税標準の特例は、家屋の床面積の10倍相当まで適用されます。
また、併用住宅で居住部分が1/4以上であるものについては、敷地に「住宅用地の率」を乗じて求めた面積まで課税標準の特例が適用されますが、その敷地面積が床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積に「住宅用地の率」を乗じて求めた面積までの適用となります。
宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、令和2年度の商業地等における負担水準は、据置特例の対象となる60%から70%までの範囲(据置ゾーン)内にほぼ収束するに至りましたが、近年の地価上昇により、令和5年度の負担水準は、据置ゾーン内にある土地の割合が低下し、再びばらついた状態となっています。
令和6年度評価替えに反映される令和2年から令和5年までの商業地の地価の状況を見ると、大都市を中心とした地価の上昇と地方における地価の下落が混在する状況が継続しています。
このため、令和6年度評価替えにおいては、大都市を中心に、地価上昇の結果、負担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加するなど、負担水準のばらつきが拡大することが見込まれるところであり、まずは、そうした土地の負担水準を据置ゾーン内に再び収束させることに優先的に取り組む必要があります。
このような状況を踏まえ、税負担の公平性等の観点から、納税者の負担感に配慮しつつ、段階的に負担水準の均衡化を進めるため、令和6年度から令和8年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みを継続することとされています。
※「負担水準」とは・・・個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
宅地の税額の求め方
課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額
課税標準額は、原則として土地の前年の課税標準額と今年の新評価額から負担水準を求め、その負担水準に応じて決定されます。
1.商業地等の宅地
商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。
| 負担水準の区分 | 調整措置(今年の課税標準額) |
|---|---|
| 70%超 | 0.7まで引き下げ |
| 60%以上70%未満 | 据え置き(1.0) |
| 60%未満 | 前年の課税標準額+価格×5%=今年の課税標準額(A) |
(ただし、(A)が価格×60%を上回る場合は価格×60%、(A)が価格×20%を下回る場合は価格×20%が今年度の課税標準額となります。)
2.住宅用地
本来の課税標準額(今年度評価額×1/6又は1/3)(以下(B))が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度課税標準額 + (B) × 5%
(ただし、上記により計算した額が、(B)×20%を下回る場合には、(B)×20%が今年度の課税標準額となります。)
お問い合わせ先
- 象潟庁舎 総務部 税務課 資産税班(電話番号0184-43-7505)
- 金浦庁舎 農林水産部 市民サービスセンター 市民サービス班(電話番号0184-38-4300)
- 仁賀保庁舎 市民福祉部 市民課 市民サービス班(電話番号0184-32-3030)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
お問い合わせはこちら






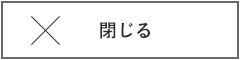

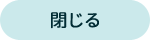
更新日:2024年12月18日