国民健康保険税
国民健康保険税(以下「国保税」と略します。)は国民健康保険(以下「国保」と略します。)加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費や介護サービスの費用に充てられる大切な財源です。国保加入者のいるすべての世帯に課税されます。
- 納める人(納税義務者)
- 国保と介護保険
- 国保税の税額
- 国保税の普通徴収(口座からの引き落とし)
- 国保税の特別徴収(年金からの引き落とし)
- 納付方法の変更(年金からの引き落とし→口座振替)
- 年度途中で異動の場合は
- 国保税の軽減
- 国保税の減免・徴収猶予
- 国保税を滞納していると
項目をクリックするとジャンプします。
納める人(納税義務者)
国保税を納める方は、国保加入者のいる世帯の世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。(これを「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」といいます。)
国保と介護保険
40歳から64歳までの国保加入者(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、国保税のうち介護分として納めていただくことになります。65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料は、年金から引き落としされるか、納付書により納めていただきます。詳しくは介護保険のページをご覧ください。
国保税の税額
(1)令和7年度の国保税
| 税率と税額(課税の基礎) | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
|---|---|---|---|
| 所得割額(課税総所得) | 6.9% | 2.7% | 2.1% |
| 均等割額(被保険者1人につき) | 34,500円 | 13,100円 | 13,300円 |
| 課税限度額 |
66万円 |
26万円 | 17万円 |
計算例は以下のファイルをご覧ください。
令和7年度国民健康保険税チラシ (PDFファイル: 142.5KB)
国保税の普通徴収(口座からの引き落とし)
国民健康保険税の口座振替の原則化について
令和3年6月、「にかほ市国民健康保険税条例施行規則」の改正に伴い、国保税の普通徴収の納付については、「口座振替による納付が原則」となりました。
これは、国保税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す取り組みの一環として実施するものです。
ペイジー口座振替受付サービスの開始
これまでの書面による口座振替申し込みに加え、令和3年10月より市役所の窓口でキャッシュカードを使って簡単に口座振替の申し込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」が利用できるようになりました。
国保への加入手続きの際、身分証明書を掲示していただき、キャッシュカードを読み取り、暗証番号を入力していただくだけで、口座振替の手続きがワンストップで完了します。届出印も不要で、金融機関に出向く手間も省くことが出来ます。納付の手間や納め忘れがなく、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください!
詳しくは以下のファイルをご覧ください。
ペイジー口座振替受付サービス (PDFファイル: 222.9KB)
国保税の特別徴収(年金からの引き落とし)
平成20年4月から高齢者医療制度の改正に伴い、年金から国保税の特別徴収(年金からの引き落とし)が始まりました。
次の条件をすべて満たす方は、年金からの引き落としにより国保税を納付していただくことになります。
年金からの引き落としとなる条件
- 世帯主が国保加入者である。
- 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
- 納税義務者(国保世帯主)の年金額(基礎年金)が年額18万円以上である。
- 介護保険料も年金から引き落としされている。
- 国保税と介護保険料との合計額が、年金受給額(基礎年金)の2分の1を超えていない。
- 今年度中に75歳となり後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、上記の条件を全て満たす場合でも年金からの引き落としにはなりません。
- 世帯内の国保資格得喪時期によっては、この限りではありません。
年金から引き落としされる金額
前年度から引き続きで年金から引き落としとなる方は、4月、6月、8月の年金からは仮徴収額として、前年度2月分と同額を引き落としします。
4月から新たに年金からの引き落としが開始される方は、前年度の年税額から介護分を差し引いた額の6分の1の額を4月、6月、8月の年金から引き落としします。
10月、12月、2月の年金からは、7月に決定する年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分の1ずつを引き落としすることになります。
納付方法の変更(年金からの引き落とし→口座振替)
国保税を年金からの引き落としにより納付されている方のうち、次の条件を全て満たす場合は、お申し出いただくことにより納付方法を口座振替に変更することができます。
納付方法を変更できる条件
- 国保税を滞納することなく納めていただいている方。
- これからの保険税を口座振替により納めていただける方。
すでに口座振替の依頼登録がお済みの方は下記窓口へお申し出ください。
まだ口座振替を登録していない方は、1・2どちらかの方法で登録をしていただく必要があります。
- ペイジー口座振替受付サービスで下記窓口にて口座振替を登録し、納付方法変更の手続きをしていただく。(注釈1)
- 金融機関(秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫・JA秋田しんせい・ゆうちょ銀行)で口座振替の申し込みをしていただき、下記窓口にて納付方法変更の手続きをしていただく。(にかほ市の金融機関であれば窓口に申込書が備えてあります。)
(注釈1)口座振替の登録は窓口に来られた方の口座のみ登録可能です。身分証明書類と登録を希望する口座のキャッシュカードを持参ください。
お申し出窓口
年度途中で異動の場合は
国保税は年度ごとに決められるので、年度の途中での国保加入や脱退のときは月割計算で求めた税額を納めていただくことになります。月割計算した結果、翌月以降の納期に税額が残る場合は、再計算した後の納付書を送付します。また、すでに納付いただいた税額よりも少なくなった場合、差額分については還付の通知を差し上げます。
途中で加入したときの保険税
保険税額=年間保険税に、加入した月から年度末までの月数を乗じて12月で除した金額
途中で脱退したときの保険税
国保税の軽減
均等割の減額制度
前年中の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保加入者の合計総所得額が一定基準額以下の場合には、税の負担を軽くするために年間保険税のうち均等割額を減額する制度があります。
| 軽減の種類 | 軽減となる世帯の合計総所得金額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 前年の世帯主および(擬制世帯主も含む)国保加入者の合計所得金額が、10万円に給与所得者等の数(注釈1)から1を除いた数を乗じて得た金額に43万円を加算した金額以下 |
| 5割軽減 |
前年の世帯主および(擬制世帯主も含む)国保加入者の合計所得金額が、29万5千円に被保険者数(注釈2)を乗じて得た金額と10万円に給与所得者等の数(注釈1)から1を除いた数を乗じて得た金額と43万円を加算した金額以下 |
| 2割軽減 | 前年の世帯主および(擬制世帯主も含む)国保加入者の合計所得金額が、54万5千円に被保険者数(注釈2)を乗じて得た金額と10万円に給与所得者等の数(注釈1)から1を除いた数を乗じて得た金額と43万円を加算した金額以下 |
- 注釈1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける者
- 注釈2)同じ世帯の中で、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
軽減の判定には、世帯の国保加入者全員及び世帯主が所得申告されていないと対象になりません。
均等割の減額を受けるための申請は不要です。
非自発的失業者に係る国保税の軽減
65歳未満で会社の倒産や会社の都合で離職した方に対する国保税の軽減制度です。
(1)対象となる方(次のすべてに該当)
- 離職年月日が平成21年3月31日以降の、雇用保険受給資格者証を持っている方。
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)のいずれかである方。
(2)軽減額
- 該当する方の前年中の給与所得を100分の30として国保税を計算します。
(3)軽減の対象期間
- 離職の日の翌日から翌年度末までの期間です。
雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
国保加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険への加入などで国保の資格を喪失すると終了します。
非自発的失業に係る軽減を受けるには申請が必要です。
(雇用保険受給者資格者証を持参して、申請して下さい。)
申請先
市民課、金浦市民サービスセンター、税務課市民サービス班
旧被扶養者の軽減(条例減免)
社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者となっていた65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国保へ加入する場合は、加入した月から以後2年を経過するまでは以下のように軽減(減免)されます。(所得割額については、2年経過後も当分の間免除されます。)
- 所得割額 免除
- 均等割額 5割軽減(ただし、所得の判定により7割軽減・5割軽減に該当する場合を除く)
所得の判定で2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割を減免
未就学児均等割額軽減(子ども軽減)
令和4年度税制改正により、平成30年4月2日以降に生まれた子どもに係る均等割額が5割減額されます。低所得者軽減の適用がある場合は、その軽減後の均等割額が5割減額されます。
軽減を受けるための申請は必要ありません。
産前産後期間に係る保険税軽減
令和5年度税制改正により、令和5年11月1日以降に出産予定の方に係る所得割額と均等割額が4ヵ月間減額されます。多胎妊娠(双子や三つ子等)の方の場合は、6ヵ月相当分が減額されます。軽減を受けるためには、産前産後期間に係る保険税軽減届出書の提出が必要です。出産予定日の6ヵ月前から届出することができ、出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類・・・届出書、母子健康手帳など
「産前産後保険税軽減リーフレット」 (PDFファイル: 485.0KB)
国保税の徴収猶予(又は減免)
下記の事由に該当し、国保税の納付が困難であると認められる場合は、税額の徴収猶予(又は減免)する制度があります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合、または、これに準ずると認められる場合
- 所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった場合、または、これに準ずると認められる場合
- 突然の災害など特別な事情がある場合
申請書提出期限は、納期限前7日までになります。
国保税を滞納していると…
特別な事情の申し出がないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
- 督促をうけたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 保険証の有効期間が短くなります。(短期被保険者証の交付)
- 医療費の負担がいったん全額自己負担になります。(被保険者資格証明書の交付)
- 保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。
- 給与や預貯金等の財産を差し押さえるなど滞納処分を行う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民国保税班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7505
お問い合わせはこちら






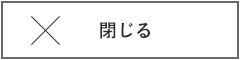

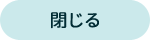
更新日:2025年11月27日